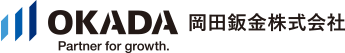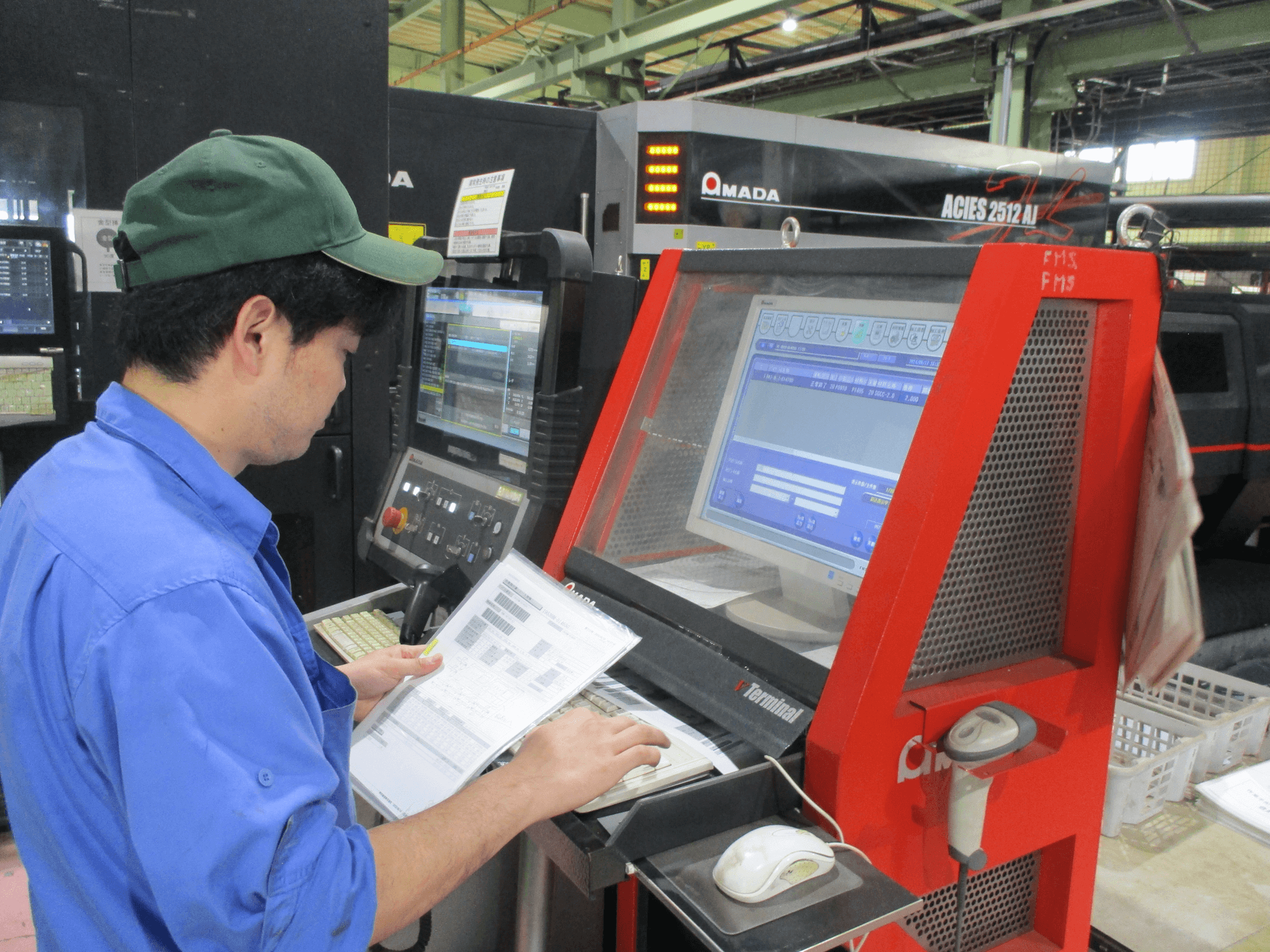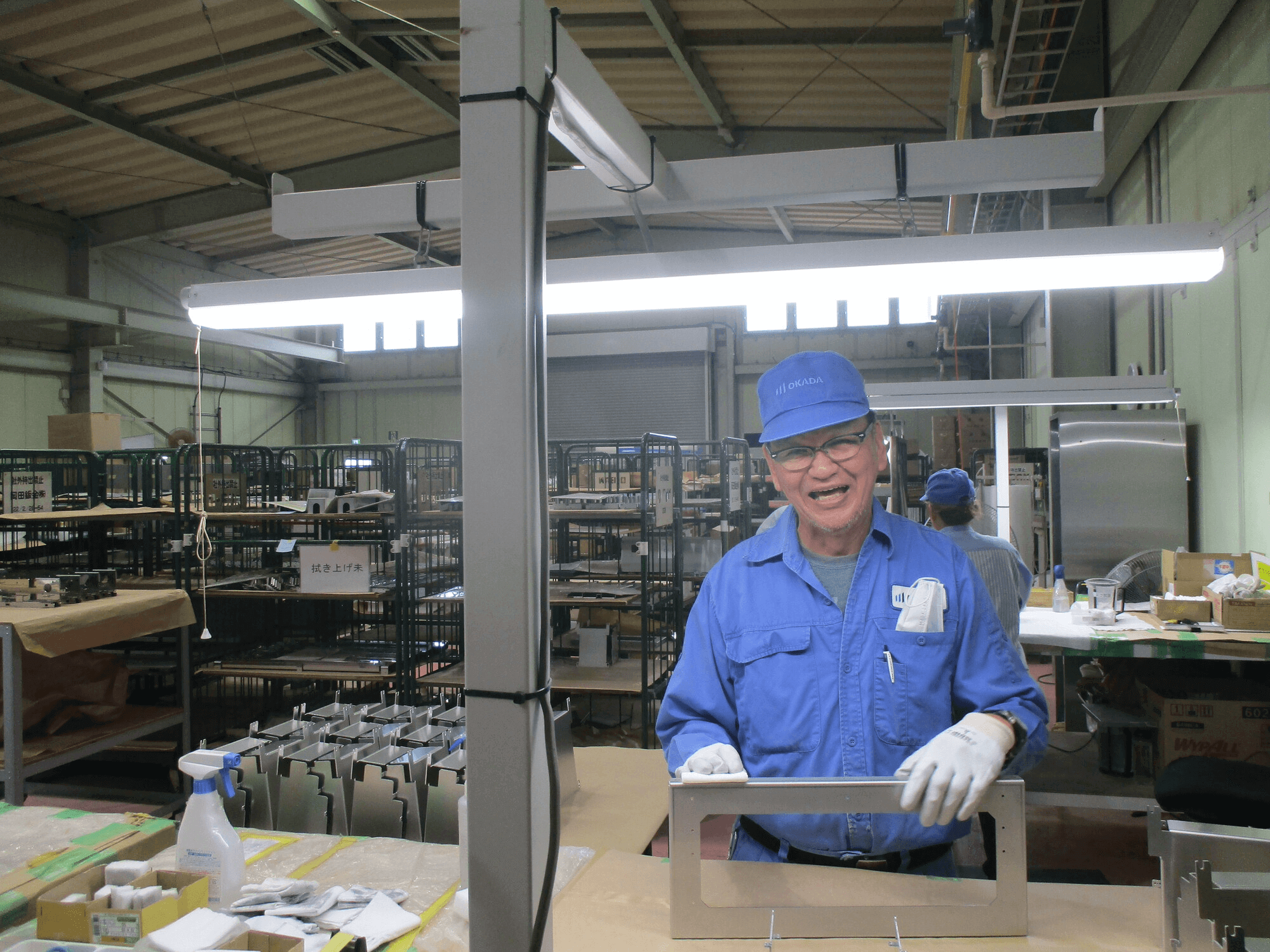キャリア形成
Career
一般職
期間:入社後7、8年程度
基礎をしっかり学んで次のSTEPへ
◆基本業務の習得
まずは基本業務をしっかり教えていきます。
どんな業務も基礎をしっかりと築くことが成長への一番の近道です。しっかりと時間をかけて、基本業務を学んでいきましょう。
◆ステップアップのための資格取得
業務の中には、資格がないと携われないものもあります。まずは資格を取得できるように、準備をしていきます。
資格を取得するための受験代金を会社で負担したり、資格が取得できるよう、会社がバックアップします。
◆活躍できる業務を見つける
様々な工程の経験の中で、自己判断、会社判断で適正を見つけ、活躍ができる業務を見つけていきます。
自分が携わる業務の前後の工程を意識することができるようになります。
リーダー・係長
期間:5、6年程度
しっかりと経験を積んで管理職へ
◆管理職のサポート
管理職のサポートをしながら、管理職に上がるための実務を学んでいきます。
依頼された業務に対して、自ら采配を考えることも必要になります。管理職への報・連・相はもちろん必要ですが、積極的に自ら考える力も身につけていきましょう。
◆新人・若手社員への指導
新人時代に上司や先輩から教えてもらったように、今度は自らが教える立場です。
自分本位にならず、相手の立場や相手の考え方を汲み取れるようにしていくことが非常に重要です。
◆仕事の割り振り・組織化 • 工程指示や納期管理
全体を見ながら仕事を割り振ったり、適切な組織化を行ったり、工程指示や納期管理といった管理業務も行っていきます。
一部に負担が傾かないよう、俯瞰で全体を捉え、バランスを考えた指示が必要となります。
もちろん現場の意見などにも耳を傾けて、しっかりと受け止めたうえで考えることが重要です。
◆勤怠管理や残業指示
現場責任者として、個々の勤怠管理も非常に重要です。組織としては、問題なく稼働している場合でも、その中にまで目を向けると特定の個人に業務が偏っていて、過負荷になっている場合もあります。全体を見つつ、細かく各個人のことにも目配りできるように心がけましょう。また、時には、業務の都合上、残業が避けられないケースもあります。そんなときにも、過度な残業や無駄な残業にならないよう、注意することが非常に大切です。
◆チーム間の連携
それぞれの組織・チームが連携することが、より業務がスムーズに進んでいきます。どこかの組織・チームだけがずば抜けて優秀でも連携はうまくいきません。それぞれの組織やチームが、バランス良くなるように采配しましょう。
最初は、上司である管理職の方とも相談しながら、徐々に慣れていきましょう。
◆スキルアップ・レベルアップ
リーダー・係長としての業務だけでなく、もちろん個人としてのスキルアップやレベルアップも同じくらい重要です。
自己研鑽を怠らず、業務に邁進しましょう。
課長・部長
期間:10〜15年程度
部門長として、責任ある行動を
◆部門の課題解決
業務の中で、大小問わず、様々な問題が発生します。すぐに解決しないと大きな影響を及ぼすことも、緊急で対処が必要なことも、すぐに解決ができない問題も、どんな問題が発生するかはわかりません。管理職として、焦らず対処することが非常に重要ですが、問題が起こることを想定して、備えておくことも等しく重要です。また、コミュニケーションをしっかり取ることで、防げる問題も多々あります。
◆部門の収支管理
経験者の視点で、収支の管理をすることも部門の責任者の重要な役割です。収支のバランスが崩れている状況だと、必ず業務上のどこかに歪みが起こっています。支出が多く、収入が少ない場合には、生産性が悪く、組織や部門の存続にも関わってくるため、バランスを整え、しっかりと部門・組織として、存在価値を高めていくのも、責任者の果たすべき責務です。
◆部門内の従業員管理
全体のバランスを見ながら、人員が多過ぎず、かつ、少な過ぎず、の適正のある人数で稼働することが重要です。そのためには、人事計画をしっかりと策定し、欠員が出てから焦って採用活動を開始しないように心がけることが必要です。
スタッフの方々にもそれぞれの事情があるため、離退職は避けられませんが、それを理解した上で、日頃からしっかりとコミュニケーションを取り、メンタルケアをすることも責任者としての大事な役割です。
◆部下の評価
部門責任者として、部下の方々の評価をするのも、責任者の重要な業務です。もちろん責任者も人なので、好き嫌いや仲の良し悪しなどもありますが、特定の個人の贔屓などに見られないように、客観的に納得のできる評価をすることが最も大事です。
不当な評価などは以ての外です。正当な評価をすることで、部下の方々のモチベーションアップや成長にもつながっていきますので、正当な評価を徹底しましょう。
◆人材配置や教育・指導 • 取引先との交渉
リーダー、係長でも、同様に行っていた業務ではありますが、部門責任者の場合は、そのリーダー・係長への教育や指導を行います。
リーダー・係長としての心構えやどう向き合うのか、どう考えて、どう行動するべきか、など模範となる現場責任者となれるように、しっかりと教育・指導を行いましょう。
また、取引先との交渉も大事な役割です。時には、新規の取引先との交渉や条件変更に伴う交渉もあります。収支のバランスにも関わってくるため、責任者としての腕の見せどころでもあります。
◆経営層と社員の橋渡し
会社組織ですから、部門を超えての異動なども、時には発生します。当然、異動する本人は不安な気持ちも抱えています。だからこそ、部門責任者として、少しでも不安が払拭できるよう努めることが非常に重要です。
異動先の責任者となる方への申し送りや、引き継ぎ事項などをしっかりと伝えることで、異動先でもこれまで以上に活躍できるよう、支援を行いましょう。
◆責任者としての意思決定
これはとても重要なことですが、部門責任者として、意思決定が必要になることが多々あります。自らの決定にきちんと責任を持って判断しましょう。部門責任者としての決定ですので、当然ですが、部門以下全員に影響があります。無責任な判断や誰かに責任を押し付けないよう注意しましょう。優柔不断な責任者は、頼りなく見えてしまいますので、自らの決定に胸を張れるようにしていきましょう。